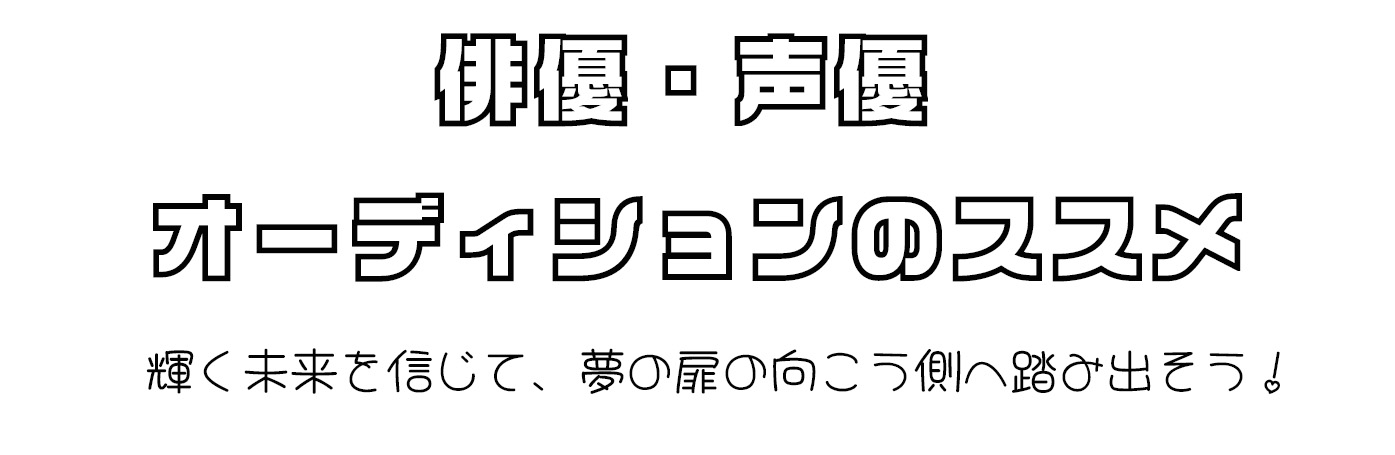「ボイトレ」に通い始めたはいいものの、「全然上達しない」「費用ばかりかかって成果を感じられない」と悩んでいませんか?
実は、ボイトレで伸び悩むのは珍しいことではありません。
特に、声優や俳優を目指す人たちは「すぐに結果を出さなきゃ」と焦りやすいですよね。
そんなとき、「もうボイトレやめちゃおうかな」と考えるのも自然な流れかもしれません。
でもちょっと待ってください。
もしかしたら、ただやり方や考え方が合っていないだけかもしれません。
そこで今回は、ボイトレをやめようか迷っている方に向けて、「効果が出ない理由」と「解決策」を具体的に紹介していきます。
ボイトレをやめたほうがいいのか?効果が出ない理由を考える

ボイトレに通った結果、なぜ効果が感じられないのか
ボイトレは、筋トレみたいなものとよく言われます。
筋肉をつけるのと同じで、声を鍛えるにはある程度の時間と地道な反復練習が必要です。
でも、がんばっているのに効果が感じられない原因には、主に以下のようなものがあります。
- 目的があいまい
「歌がうまくなりたい」「発声をよくしたい」という願望はあっても、具体的にどんな声が出せるようになりたいのかが不明確だと、練習が散漫になりがちです。 - 練習方法が自分に合っていない
体の作りや声帯の形状は人それぞれ違うため、誰かに合う練習法が自分にピッタリ合うとは限りません。
自分の弱点に合ったメニューを組んでいないと、思うように成果が出ないことが多いです。 - 声の使いすぎ・使わなさすぎ
忙しくて発声練習をサボってしまったり、逆に無理をして声を酷使してしまうと、声の調子が安定しません。
適度な練習量と休息のバランスが大切です。
月2回のボイトレで効果がない場合の理由
「月2回」のボイトレは、歌える俳優を本気で目指す場合には頻度として少ないかもしれません。
これから目指す段階では、理想的には週1回、少なくとも10日に1回程度のペースで客観的な指導を受けることが効果的です。
可能であれば月3回以上のレッスンを目指すことで、着実な成長が期待できます。
- 自宅練習をしていない
ボイトレのレッスンは、いわば「方向性を確認する場所」です。
そこで学んだことを日常で実践しないと、次のレッスンまでに体が進化しません。
レッスンの時間外にどれだけ自分を鍛えるかが勝負です。 - 集中力が続かない
月2回のレッスンだと、1回1回の内容が濃いものになる必要があります。
でも、疲れていたり気持ちが乗っていないと、レッスンを消化するだけで精一杯になってしまうことも。 - レッスン内容を忘れてしまう
月2回だと「前回の指導を忘れちゃった…」ということも起こりやすいです。
メモを取ったり録音したりして、次までに学んだことを思い出して練習する工夫が必要です。
1年続けても効果を感じない場合に考えるべきこと
1年というのは、声を鍛えるうえではそれなりに長い時間です。
にもかかわらず「全然変化がない」と感じる場合は、以下の点を振り返ってみてください。
- 指導者との相性
ボイトレ講師も人それぞれ教え方が違います。
自分の目標と講師の得意分野や指導スタイルが合っていないと、結果が出にくいことがあります。 - 練習量と方法を見直す
正しい方法を継続的にやっているかどうか、練習時間は十分かどうか再確認しましょう。
楽しく取り組めるメニューに変えてみるのも手です。 - モチベーションが低い
「やらなくちゃ」という義務感ばかりだと、思った以上にパフォーマンスが上がりません。
まずは、自分がその練習で何を得たいのかをもう一度はっきりさせてみてください。
ボイトレで効果を出すためのポイントと解決策

自分に合ったボイトレの選び方とは?
- 得意分野を見極める
講師によっては、オペラ唱法に詳しい人もいれば、演劇の発声に強い人もいます。
自分が求める方向性と講師の得意分野が合致しているかが大事です。
まずは体験レッスンで雰囲気や教え方をチェックしてみましょう。 - レッスンの場所・時間帯を考える
自宅から遠いスタジオに通う場合、通うだけで疲れてしまうこともあります。
続けるためには通いやすい環境が重要です。 - フィードバックの仕方
「ここが悪い」とダメ出しばかりする講師と、「こうするともっと良くなるよ」と解決策を具体的に示してくれる講師では、伸び方が変わってきます。
指導方法が自分と合うかどうかもしっかり確認しましょう。
ボイトレで「恥ずかしい」と感じる人へのアプローチ
発声練習は声を大きく出したり、変わった音を出すことも多いので、人によっては恥ずかしいと感じるかもしれません。
そんなときの対処法は、
- 部屋の防音対策をする
自宅での練習でも、声が漏れにくい環境を作れば思い切り声を出しやすくなります。
マンションの方は防音カーテンや防音マットを使うだけでもかなり変わります。 - 小さな声から始める
いきなり全力で声を出す必要はありません。
まずは小さい声でフォームを作ってから、徐々に声量を上げていけば気持ちのハードルが下がります。 - オンラインレッスンを活用
対面レッスンが恥ずかしい人には、オンラインレッスンという方法もあります。
自宅で周りを気にせず練習できますし、移動時間の心配もありません。
ボイトレで歌が上手くなるために必要な練習方法
- ブレス(呼吸)の練習
歌は呼吸が命。
腹式呼吸をしっかり身につけることで、声が安定しやすくなります。
寝転がってお腹に手を当てながら、息をゆっくり吸ったり吐いたりする練習から始めてみましょう。 - 音程を正確にとるトレーニング
ピアノアプリや電子キーボードを使って、自分の歌う音が合っているかチェックしましょう。
スマホアプリでも「音程チェック」をしてくれるものがあります。 - 表現力を意識した歌唱練習
歌詞の意味をしっかり理解して、感情を込めることも大切です。
ただ音を取るだけでなく、どんな気持ちで歌うかをイメージしてみると、声の響き方が変わります。
声帯の使い方を理解して効果を最大化する
声帯は、筋肉と粘膜でできています。
無理に力を入れると喉を痛めたり、逆に声が細くなったりします。
ポイントは、
- リラックスして声帯を振動させる
首や肩に力が入っていると、声帯も動きにくくなります。
ストレッチなどで上半身をほぐしてから練習を始めましょう。 - 息の流れと声帯のバランス
息を多く出しすぎると声帯がブレてしまいますし、逆に少なすぎると声が詰まったりかすれたりします。
息と声帯のバランスを探りながら、適度な量を意識してください。 - 身体全体で響きを感じる
声は喉だけで作るものではありません。
胸、口、鼻腔(びくう)など、さまざまな共鳴スペースを使って響きを作ります。
声を出したときにどこが振動しているかを意識してみてください。
【まとめ】ボイトレをやめたほうがいい?続けるためのポイント
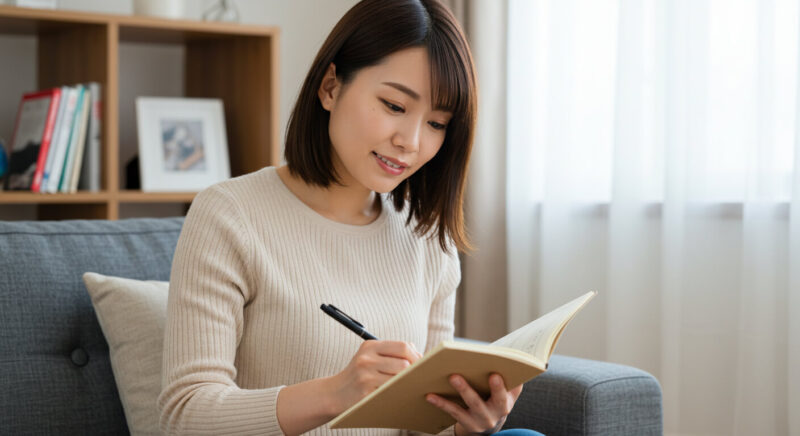
ボイトレを続けるべきかやめるべきかの判断基準
- 明確な目標や夢があるか
もし声優や歌える俳優として本気で活躍したいなら、声のスキルは必須です。
遠回りでも続ける価値は大きいでしょう。 - 指導者や練習環境が自分に合わないだけでは?
やめる前に、他の教室や講師を探してみるのもありです。
環境を変えたら一気に伸びるケースもあります。 - 費用と時間のバランス
経済面や時間が厳しいときは、一時的に自己流で鍛える方法を考えてみるのも手です。
今はオンライン教材やアプリも充実しています。
ボイトレで成果を出すための実践的なアドバイス
- レッスン内容を必ず復習する
指導者から受けたアドバイスは、その日のうちにメモしたり録音を聞き直して復習する習慣をつけましょう。 - 毎日5分でも練習時間を確保する
短時間でも継続することが大事。
歯磨きと同じように習慣化すれば上達が早くなります。 - 自分の声を録音して客観的に聞く
最初は恥ずかしいかもしれませんが、録音を聞くことで客観的に改善点を見つけやすくなります。 - 成長記録をつける
ノートやスマホのメモを使って、自分がどこまでできるようになったかを記録してください。
小さな変化でも成長を実感できれば、やる気が持続します。
ボイトレで伸び悩むのは、決して珍しいことではありません。
教室や講師、練習方法が自分に合っていないだけであったり、目標がはっきりしていないことが原因かもしれません。
特に声優や俳優志望なら、声のトレーニングは武器になります。
「やめるか迷っている」方こそ、一度しっかり自分の目的やこれまでの練習方法を見直してみてください。
もしかしたら、もう少し続ければ伸びる可能性があるかもしれません。
環境を変えたり、アプローチを変えたり、まずはそこから始めてみましょう。